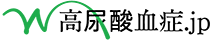肥満または肥満症の合併を考えたレシピ③
包丁いらずの減塩炊き込みごはん
(監修)
帝京平成大学薬学部教授 金子希代子 先生
株式会社フォーラル 管理栄養士 孰賀佳冬 先生

肥満または肥満症を合併する高尿酸血症・痛風の患者さんにお勧めするレシピの3回目です。1回目は副菜のしらたきサラダ、2回目は主菜の揚げない肉団子でした。3回目は新アイデアの低カロリー炊き込みご飯で、食物繊維が多いので良く嚙むことで満腹感が得られ、摂取エネルギーを減らすことに繋がります。
- 白米
- 1カップ
- 押し麦
- 1/2カップ
- しめじ
- 1袋
- まいたけ
- 1パック
- きんぴらごぼうの素
- 1袋
- 油揚げ
- ひと握り
- 和風顆粒だし
- 小さじ1
- しょうゆ
- 小さじ1
- 小ねぎ
- お好みで
1人分
- エネルギー
- :257kcal
- 食物繊維
- :6.1g
- たんぱく質
- :7.4g
- 食塩相当量
- :0.6g
- 脂質
- :3.5g
- プリン体量
- :60.4mg
- 糖質
- :47.0g
エネルギー産生栄養素バランス(PFC)=P:11.4% F:12.2% C:76.3%
※エネルギー産生栄養素バランス(PFC):エネルギーを産生する栄養素(Protein:たんぱく質・Fat:脂質・Carbohydrate:炭水化物)のエネルギー比率を示したもの
- 白米を洗い、一合分の水量で水を入れる
- 押し麦を加え、押し麦の倍量の水を加えよく混ぜる
- 和風顆粒だしを加えて混ぜたあと、具材を全て入れて炊飯する
- 炊きあがったらよく混ぜ合わせ、しょうゆを加えて再度よく混ぜる
- お椀に盛り、お好みで小ねぎを乗せてできあがり
切って下ごしらえもできている食材を使った包丁いらずの炊き込みごはんです。
噛み応えのある食材が多いので、早食いを防ぐことができます。
ごはんに味を染み込ませやすい食材と、コクの出る食材を選びました。
最後にしょうゆを混ぜることで、表面に味をつけてぐっと塩分量を減らしました。
肥満は体の状態を、肥満症は疾患を表し、肥満症とは『肥満に起因ないし関連する健康障害を合併するか、その合併が予測され、医学的に減量を必要とする病態』と定義されています(1)。肥満症の原因は内臓脂肪の過剰蓄積であることがわかっており、内臓脂肪を減らすことで合併する糖尿病や高血圧、脂質異常症などの健康障害が改善されます。体格指数(BMI)*≧25の場合は、まず体重を減らすことを考えましょう。体重や体脂肪率が高いほど、血清尿酸値が高いことも報告されています。目標とするBMIは、65歳未満の方はBMI<22、65歳以上の方は22≦BMI<25 とされています。
肥満症診療ガイドライン2022(1)によると、肥満症の減量目標は3~6か月で現体重の3%です。体重100kgの人が3~6か月で3kgの減量と考えると決して無理な数字ではない気がします。減量には、食事療法、運動療法、行動療法などが上げられており、食事療法が基本になります。食事療法では、(1)摂取エネルギーを減らす、(2)指示エネルギーの内訳は、炭水化物50~65%、蛋白質13~20%、脂肪20~30%、(3)必須アミノ酸を含む蛋白質、ビタミン、ミネラルの十分な摂取、(4)十分な食物繊維の摂取、等が勧められています。
そこで、今回のレシピは、低エネルギーで、食物繊維を多く含む炊き込みご飯にしました。使われているごぼうもきのこ類も、プリン体は少なく、食物繊維を多く含みます。また、肥満症患者は荒噛みで早食いであることが多く、行動療法の中にそれらについての食行動質問も入っています。今回のレシピは、良く噛むことも意識して考案されていますので、是非、よく噛みゆっくり食べることを意識して、健康な生活を送って下さい。
* :BMI=体重(kg)÷(身長(m))2
(1) 肥満症診療ガイドライン2022。日本肥満学会編集。ライフサイエンス出版、2022年12月